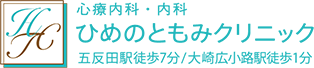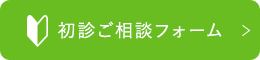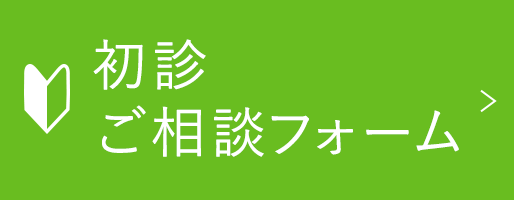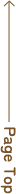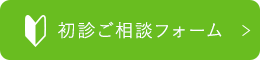適応障害(適応反応症)とは

適応障害(適応反応症)とは、自分にとって強すぎるストレスを受けたことにより、その状況にうまく対応できなくなり、心や体、行動に支障をきたしてしまう状態です。症状が日常生活に影響を与えるほど強くなることもあります。
ストレスの原因は、国際的な出来事のような大きなものから、身近な人間関係まで様々です。また、どのような症状が現れるかも個人差があります。
この障害の特徴は、「何がストレスになっているか」が比較的明確な点にあります。そのため、医師の適切なサポートのもとでストレスの原因から距離を置くなどの対応を取ることで、以前のような日常生活を取り戻すことも十分に可能です。
適応障害はどんな症状?
- 1つのことにとらわれ、ずっと考え続けてしまう
- 集中力が続かず、仕事や勉強でミスが増える
- 遅刻や欠勤を繰り返すようになる、無断で休んでしまう
- 感情の起伏が激しくなり、自分でコントロールできなくなる
- 暴飲暴食など、衝動的な行動が増える
- 休日などストレスから離れた環境では気分が軽くなる
- イライラが爆発し、物に当たって壊してしまう など
適応障害の原因
適応障害は、就職・転職、昇進、配置転換、転校、クラス替え、引っ越しなど、日常生活における環境の変化がきっかけとなり、その人にとって耐えがたいほど強いストレスがかかったときに発症することがあります。ストレスが心や体の限界を超えることで、防御反応がうまく働かなくなり、精神的・身体的な様々な症状が起こります。適応障害の特徴は、症状の背景にあるストレスの原因が明確な点です。
「適応障害」と「うつ病」
「適応障害」と「うつ病」は、どちらも精神的な不調を伴うため混同されやすいですが、根本的な原因が異なります。適応障害は、特定のストレスが直接の原因となって心身の不調が現れる一方で、うつ病は脳の機能的な異常が背景にあり、ストレスは発症の引き金にはなっても根本原因ではありません。また、適応障害の場合はストレスの原因が取り除かれたり、環境を変えて距離を置いたりすることで症状が改善する傾向がありますが、うつ病ではストレス要因を取り除いても症状が継続することが多く、脳の状態そのものを治療する必要があります。このように、診断や治療においてはそれぞれの違いを正しく理解し、適応障害ではストレスの軽減を、うつ病では脳の機能回復を目指したアプローチが重要となります。
適応障害の診断基準
適応障害は、ICD-10やDSM-5といった国際的な診断基準に基づいて診断されます。具体的には、次の4つの条件が主な診断基準とされています。
- ストレスの原因が明確であり、そのストレスを受けてから3ヶ月以内に症状が起こる
- 強い苦痛や日常生活への支障が認められる
- 他の精神疾患や、愛する人との死別などによる正常な悲しみ(死別反応)ではない
- ストレスの原因から離れることで症状が軽減し、6ヶ月以内に回復する
適応障害の特徴は、原因となるストレスがはっきりしており、それを取り除くことで症状が改善する点にあります。
そのため、「ストレスの原因が自分でもはっきりしないが、心身ともに不調が続いている」という場合は、適応障害ではなく他の精神疾患の可能性が考えられます。
適応障害の治し方
 適応障害の治療では、まず患者様に強い負担をかけているストレスの原因を取り除いたり、できるだけ軽減することが基本となります。適応障害はストレスの要因が明確であることが多いため、その環境から一時的に離れることが有効であり、例えば休職や休学を勧める場合もあります。ただし、ストレスの原因をすぐに取り除けないケースも少なくありません。そのような場合には、認知行動療法などを通じて物事の捉え方や考え方を柔軟にし、ストレスの感じ方そのものを和らげていくアプローチが行われます。
適応障害の治療では、まず患者様に強い負担をかけているストレスの原因を取り除いたり、できるだけ軽減することが基本となります。適応障害はストレスの要因が明確であることが多いため、その環境から一時的に離れることが有効であり、例えば休職や休学を勧める場合もあります。ただし、ストレスの原因をすぐに取り除けないケースも少なくありません。そのような場合には、認知行動療法などを通じて物事の捉え方や考え方を柔軟にし、ストレスの感じ方そのものを和らげていくアプローチが行われます。
適応障害の人にかける言葉
適応障害の方と接する際には、相手の気持ちに寄り添い、安心できる言葉をかけることが大切です。全ての人に同じ言葉が効果的とは限りませんが、以下のような声かけは、気持ちを支えるきっかけになるかもしれません。
「何かあったら、いつでも話を聞くからね」
「今は無理しなくて大丈夫。安心してゆっくり休んでね」
「これまで本当によく頑張ってきたね」
「できることは何でも力になるから、1人で抱え込まないでね」
また、周囲にいる人ができるサポートには、「相手の小さな変化に気づくこと」や、「できる範囲で環境を調整すること」があります。
適応障害について正しく理解し、無理のないサポートを続けることが、早期回復への助けになります。
適応障害の人に言ってはいけない言葉
適応障害の方に対しては、励ますつもりでかけた言葉が、かえってプレッシャーになったり、傷つけてしまうことがあります。
以下のような言葉は避けるようにしましょう。
「それって甘えじゃない?」
「気持ちの問題なんじゃないの?」
「もっとつらい思いをしている人だっているよ」
「元気出して頑張らなきゃ」
「これからどうするつもりなの?」
適応障害は休むべき?
適応障害は、原因となるストレスが取り除かれることで回復が期待できますが、ストレスの状況が改善されないまま長引くと、症状が慢性化し、うつ病など他の精神疾患を併発してしまう恐れがあります。こうしたリスクを避けるためにも、適応障害と診断されたら、まずは無理をせず回復を最優先に考えることが大切です。
ストレスから距離を置き、心と体をしっかり休めるためには、休職という選択も前向きな一歩です。休職を希望する場合には、精神科や心療内科などの専門医による診断が必要となります。そのうえで、職場の上司や人事・労務担当、産業医などと相談しながら、休職の手続きや復職に向けた流れを確認しておくと安心です。復職時の条件を事前に把握しておくことで、再スタートもスムーズになります。
なお、周囲の言葉や態度が本人にとって負担になることもあります。何気ない一言で深く傷ついてしまうことがあるため、相手を思いやる気持ちを忘れずに接することが大切です。