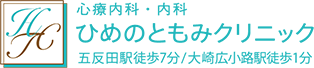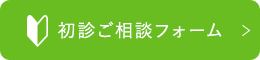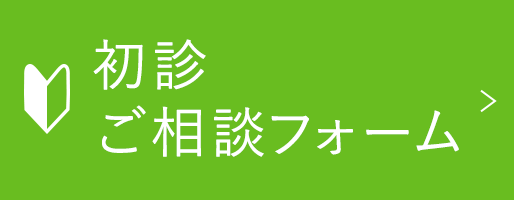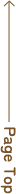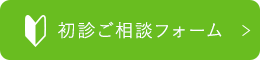不安障害の症状をチェック
不安障害では、様々な身体的・精神的な症状が現れます。例えば、動悸や発汗といった体の反応のほか、理由もなく強い不安や恐怖に襲われるといった心の症状も見られます。
身体症状
- 動悸がする、心拍数が急に上がる
- 発汗が増える
- 呼吸が苦しくなる、息切れ
- 窒息しそうな感覚に襲われる
- 手足や体が震える
- 胸の痛みや圧迫感、胸苦しさを感じる
- 吐き気や腹部の不快感が続く
- めまいやふらつき、意識が遠のくような感覚がある
精神症状
- はっきりとした理由はないのに不安が続く
- 緊張状態が続いてリラックスできない
- 落ち着きがなく、そわそわしてしまう
- 周囲の刺激に敏感に反応してしまう
- 集中力が続かない
- ちょっとしたことでイライラしたり、怒りっぽくなる
不安障害で悩んでいる方に対して、ご家族や周囲の方は「心配しなくても大丈夫」と軽く受け止めてしまうことがあります。しかし、本人にとっては強い不安やストレスが続いており、つらさを感じていることも少なくありません。
もし、自分ではどうにもならない不安が続いていると感じたら、1人で抱え込まずに、一度当院へご相談ください。
不安障害とは
不安とは、私たちが危険を察知し、身を守るために備わっている自然な反応です。この「警戒のサイン」があることで、私たちは危険を回避したり、備えたりすることができます。
ただし、不安障害ではこのサインが過剰に働き、本来危険ではない場面でも強い不安や恐怖を感じてしまいます。その結果、日常生活や仕事、人間関係に支障が出ることがあります。
例えば、人前で話すことや意見を伝える場面で、不安を感じるのは誰にでもあることですが、不安障害の方はそうした状況で強い緊張や恐怖を感じやすく、それが日常生活に影響を及ぼす場合もあります。
社交不安障害(社会不安障害、SAD)
 人前で恥ずかしい思いをするのではないかと感じて、不安になったり緊張したりするのは、誰にでもあるごく自然なことです。しかし、社交不安障害では、その不安や緊張の度合いが非常に強く、顔の紅潮、発汗、腹痛、手足の震えなどの身体症状が現れることがあります。
人前で恥ずかしい思いをするのではないかと感じて、不安になったり緊張したりするのは、誰にでもあるごく自然なことです。しかし、社交不安障害では、その不安や緊張の度合いが非常に強く、顔の紅潮、発汗、腹痛、手足の震えなどの身体症状が現れることがあります。
このような状態は、かつて「対人恐怖症」「赤面恐怖症」「視線恐怖症」などと呼ばれることもありました。さらに、「また同じような症状が出たらどうしよう」といった不安や恐怖が重なり、人と会うことを避けたり、外出を控えたりするようになるケースも少なくありません。
全般性不安障害(GAD)
全般性不安障害は、特定の出来事や状況に限らず、日常生活全体にわたって漠然とした不安や心配、緊張が半年以上続く状態です。
例えば、「自分が大きな病気になるのではないか」「家族が事故に巻き込まれるのではないか」といった、健康や事故、災害に関することなどを過度に心配してしまい、その不安が頭から離れなくなることがあります。
こうした不安が続くことで集中力が低下し、疲れやすさや筋肉のこわばり、震え、多汗、不眠、吐き気、下痢、動悸、めまい、頭痛などの身体的な症状が現れることもあり、日常生活に大きな影響を及ぼします。
強迫性障害(強迫神経症)
強迫性障害とは、頭から離れない強い不安や不快感(強迫観念)にとらわれ、それを解消しようとして過剰な行動(強迫行為)を繰り返してしまう精神疾患です。
例えば、「手が汚れているのではないか」という不安にとらわれ、過剰に手を洗い続けてしまうといった行動が見られることがあります。
不安障害の治療法
 不安障害は、原因や症状の現れ方によっていくつかのタイプに分かれており、患者様の状態に合わせて進めていくことが早期回復の近道です。
不安障害は、原因や症状の現れ方によっていくつかのタイプに分かれており、患者様の状態に合わせて進めていくことが早期回復の近道です。
治療には、薬物療法と精神療法などがあり、必要に応じて組み合わせて進めていきます。
薬物療法
不安障害では、脳内のセロトニンの働きが関係しているとされており、治療には抗不安薬や抗うつ薬がよく用いられます。これらのお薬には様々な種類があり、症状の程度や体質に応じて、適切なお薬を適切な量で使うことが大切です。
また、症状によっては漢方薬が有効な場合もあります。
行動療法
不安障害の治療には、お薬に頼らない方法として認知行動療法がよく用いられます。この療法は、考え方や行動のクセを見直しながら、不安をコントロールできるようにする治療法で、薬物療法と同じくらいの効果が期待される場合もあります。ただし、本人の取り組みや継続がとても大切になります。
具体的な方法としては、不安を感じやすい状況を段階的に再現し、徐々に慣れていくエクスポージャー(暴露療法)や、人との関わり方を練習するソーシャルスキルトレーニングなどがあります。こうしたトレーニングを通じて、不安を引き起こす場面でも落ち着いて対応できるよう、自分自身で対処力を身につけていきます。
パニック障害
 パニック障害は、明らかな身体の疾患がないにもかかわらず、突然動悸や呼吸困難、めまいなどの発作(パニック発作)を繰り返す疾患です。不安障害の一種であり、「また発作が起きるのではないか」という強い予期不安が日常生活に影響を及ぼします。
パニック障害は、明らかな身体の疾患がないにもかかわらず、突然動悸や呼吸困難、めまいなどの発作(パニック発作)を繰り返す疾患です。不安障害の一種であり、「また発作が起きるのではないか」という強い予期不安が日常生活に影響を及ぼします。
発作を繰り返すうちに、外出や乗り物の利用が難しくなるなど、行動範囲が制限されるようになり、仕事や人間関係にも支障をきたすことがあります。症状が長引くと、うつ病を併発することもあるため、できるだけ早い段階で専門医に相談し、適切な治療を受けることが大切です。
日頃からストレスを溜め込みやすい環境にいる方は特に発症しやすく、パニック障害は100人に1〜2人の割合で見られる比較的身近な病気と言えます。
パニック障害の症状・初期症状
パニック障害の原因は、脳内の神経伝達物質のバランスの乱れ特に、感情やストレスの調整に関わるノルアドレナリンやセロトニンといった物質が関係しています。
また、関連のある「広場恐怖症」については、過去の恐怖体験や強いストレスが心に影響を与え、自律神経の乱れを引き起こすことで発症するケースが多いとされています。
また身体的には低血糖が背後にあることが多くみられます。
精神面の症状
- 自分が自分でないような感覚にとらわれる
- 意識が遠のいていくような、気を失うことへの強い恐怖
- 「このまま死んでしまうのではないか」と感じるほどの不安
- 「また発作が起きるかもしれない」という先回りした強い不安(予期不安)
- 発作が起きた場所や状況が怖くなり、避けるようになる(広場恐怖)
身体面の症状
- 心臓が激しくドキドキし、強い動悸を感じる
- 息切れや息苦しさが突然現れ、呼吸がつらく感じる
- 急に汗が出てくる
- のどに詰まり感があり、息を吸うのも吐くのも苦しいと感じる
- 胸のあたりに痛みや圧迫感、不快感が生じる
- お腹に急な不快感や違和感が現れる
- 吐き気を感じる
- 肩こりや筋肉の緊張が強くなる
- 手足や体全体が震えてしまう
- 手足や体に痺れを感じる
- めまいやふらつき、気が遠くなるような感覚がある
- 頭痛が現れることもある
パニック障害の原因・きっかけ
パニック障害の原因は、現在のところまだ完全には解明されていません。ただし、近年の研究によって、脳内の神経伝達物質のバランスの乱れが発症に関係していることが明らかになってきています。特に、感情やストレスの調整に関わるノルアドレナリンやセロトニンといった物質が深く関係していると言われています。
また、関連のある「広場恐怖症」については、過去の恐怖体験や強いストレスが心に影響を与え、自律神経の乱れを引き起こすことで発症するケースが多いとされています。
なお、パニック障害や広場恐怖症は、遺伝する病気ではなく、誰にでも起こりうる心の不調です。
予期不安
パニック発作は、本人にとって命の危険を感じるほど強い恐怖を伴うことがあります。そのため、「また発作が起きたらどうしよう」「外出先で倒れたらどうしよう」といった不安や恐怖が心に残り、常に発作を警戒してしまうようになります。こうした状態を「予期不安」と呼びます。たとえ発作が何度も起きていなくても、予期不安の状態が1ヶ月以上続いている場合は、パニック障害と診断されることがあります。また、広場恐怖症では、予期不安をきっかけに人が多く集まる場所や発作が起きた場所を避けるようになることが、主な症状として現れます。
このような予期不安は、「心が弱いから起こる」のではなく、脳や心の仕組みによって生じるれっきとした障害の1つです。無理に我慢せず、早めに当院までご相談ください。
パニック障害の治し方
パニック障害の治療では、薬物療法と認知行動療法を中心に進めていきます。
認知行動療法は、「ものの見方」や「考え方のクセ(認知のゆがみ)」を少しずつ見直していく治療です。
薬物療法
パニック障害の治療では、まず脳内の神経伝達のバランスを整えるために抗うつ薬(SSRI)が使われることが多く、これが治療の基本となります。SSRIにはいくつかの種類があり、その中からパニック障害に適したお薬が選ばれます。
必要に応じて、一時的な不安や緊張を和らげるために抗不安薬が処方されることもあります。この場合は、即効性のあるベンゾジアゼピン系のお薬が使用されることが一般的です。
公認心理士によるカウンセリング
パニック障害の治療にはお薬を使った方法がありますが、それだけでは十分な効果が得られないケースもあります。お薬に頼りすぎず、不安を感じる状況からあえて逃げずに向き合う姿勢が、治療の中で重要になります。
そうしたときに役立つのが、心理士によるカウンセリングです。お薬を使わない治療法として、「認知行動療法」や「暴露療法」などが行われ、パニック障害への理解を深めながら、不安への対処力を高めていきます。これらの方法は、薬物療法と併せて取り入れることで、より効果的な治療に繋がります。
認知行動療法
認知行動療法は、パニック障害に伴う広場恐怖などで行動が制限されてしまっている場合に、特に効果的とされています。できなくなっている行動に少しずつ取り組み、サポーターやご家族、信頼できる人と一緒にチャレンジすることで、「できた!」という達成感や安心感を積み重ねていきます。
こうした成功体験を繰り返すことで、「不安はあっても自分には乗り越えられる」「思っていたより大丈夫だった」といった前向きな気持ちが育まれ、次第に不安の軽減や行動範囲の回復へと繋がっていきます。
なお、小さなお子様の場合は、まずお薬によってパニック発作の症状をある程度コントロールできるようになってからでないと、認知行動療法を始めるのは難しいとされています。
暴露療法(エキスポーシャー)
暴露療法は、パニック発作を経験した場所や状況に、あえて繰り返し向き合うことで、不安に少しずつ慣れていく治療法です。実際の場面で行う場合もあれば、頭の中で想像しながら取り組む場合もあります。
何度もその場面を体験することで、不安を感じても「発作は起きない」「起きても対処できる」といった感覚が身についていきます。こうして少しずつ恐怖心が和らぎ、やがては発作が起きた場所でも落ち着いて過ごせるようになることが目標です。
パニック発作の落ち着かせ方
パニック発作が起こったときは、まずは慌てずに気持ちを落ち着けることが大切です。ゆっくりと深呼吸をして呼吸を整えたり、不安から意識をそらすために周囲の音や景色などに目を向けてみましょう。必要に応じて、頓服薬を服用するのも効果的です。また、静かで安心できる場所へ移動することも、気持ちを落ち着ける助けになります。
深呼吸
- 鼻からゆっくり息を吸い、口からゆっくり吐き出します
- 「4秒かけて吸って、6秒かけて吐く」といったように、呼吸のリズムを決めて行うと効果的です
- 目安としては、6秒に1回のペース(1分間に10回程度)で、落ち着いた呼吸を続けてみましょう。慣れてきたら、「4秒かけて吸い8秒かけて吐く」といった吸気:呼気を1:2になるようにもっていきます。つまり1分間に5回の呼吸です。
違うことへ意識を向ける
- 時計の秒針を見ながら、数を数えて呼吸のリズムを整える
- 指を折りながら、順番に数字をカウントしていく
- 簡単な計算を頭の中で続けてみる
- 声に出さず、頭の中で好きな歌をくり返し思い浮かべる
その他
- イスに座ったり、壁や手すりなどにもたれかかる
- 乗り物や室内では、すぐに移動できるように出口付近の席にいるようにする
- 静かで安心できる場所に移動する
- 頓服薬を服用する