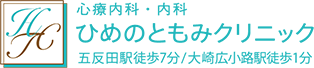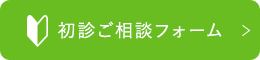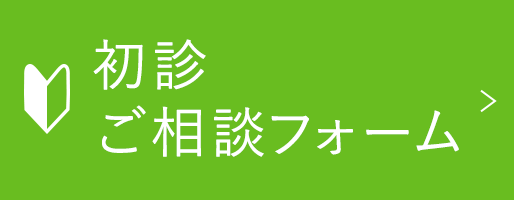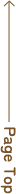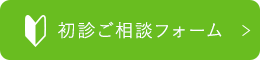慢性疲労症候群(CFS)とは
慢性疲労症候群(Chronic Fatigue Syndrome:CFS)は、強い疲労感が6ヶ月以上も続き、日常生活に支障をきたす状態が続く疾患です。体を動かすのもつらいほどの疲労感があるのに、明確な原因が見つからないのが特徴です。
この病気が医学的に提唱されたのは1988年で、アメリカの疾病予防管理センター(CDC)によって「慢性疲労症候群」という名称が初めて示されました。比較的新しい病気のため、まだ一般にはあまり知られていないのが現状です。
発症のきっかけとしては、風邪や気管支炎などをきっかけに、回復後も風邪のような症状が長引くケースがよく見られます。しばらく休んでも回復せず、不眠や食欲不振、気分の落ち込みなどを伴うようになることもあります。
最初は「風邪が長引いているのかな」と思っていた症状が、改善せず、他の病気とも違うようだと感じて初めて、異変に気づくことも少なくありません。
様々な検査を受けても内臓やホルモン、神経に異常が見つからない場合、慢性疲労症候群の可能性が考えられます。
慢性疲労症候群の症状
以下が主な症状です。
- 風邪にのようなのどの痛みや微熱などの症状
- 筋肉痛
- 関節痛
- 頭痛
- 首や脇下のリンパ節の腫れ、圧痛
- 胃腸の働きが不安定になる
- 集中力・記憶力の低下
- 睡眠障害
- 低血圧
- 体温調節がうまくいかず、暑さ・寒さに敏感になる
- 光や音に対して敏感に反応する
慢性疲労症候群は
寝てばかり?
慢性疲労症候群では、わずかな動作でも強い疲労感を感じるようになり、結果として日中も横になって過ごす時間が増えることがあります。そのため、「いつも寝てばかりいる」と見られてしまうこともありますが、単に長く眠っているからといって必ずしもこの病気とは限りません。
ポイントは、十分に睡眠や栄養をとっても体のだるさが続き、生活や仕事にまで支障が出ているかどうかです。こうした状態が長期間続いている場合には、慢性疲労症候群の可能性が考えられます。
診断にあたっては、まず内科的な病気がないかを確認し、そのうえでうつ病などの精神疾患が否定された場合に、慢性疲労症候群と診断されることが一般的です。
慢性疲労症候群の原因
慢性疲労症候群の原因は、まだ完全には解明されていません。ですが、最近の研究によって、発症のメカニズムに関する理解が少しずつ進んできています。
私たちの体は、自律神経・ホルモン・免疫という3つのバランスによって健康を保っています。しかし、強いストレスをきっかけにこのバランスが崩れると、免疫力が低下し、体内に潜んでいたウイルスが再び活性化することがあると考えられています。
このウイルスを抑えるために、体は免疫物質を大量に作り出します。ところが、この免疫反応が過剰になると、脳の働きにも影響を与え、炎症が発生するとされています。その結果、強い疲労感や様々な不調が現れるのではないか、という説が有力です。
そのため最近では、慢性疲労症候群は「筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)」と呼ばれ、脳の炎症も関係する病気として認識されつつあります。
慢性疲労症候群は何科?
慢性疲労症候群の可能性があると感じたら、まずは内科を受診して、疲労の原因となる身体の病気がないかを調べることが大切です。検査で異常が見つからなかった場合は、心療内科や精神科に相談することをお勧めします。
当院では内科と心療内科が併設しております。お気軽にご相談ください。
慢性疲労症候群の検査
慢性疲労症候群の診断では、まず身体や心の病気が原因ではないことを確認する必要があります。そのため、以下のような基本的な検査を行います。
- 血液検査
- 尿検査
- 便検査
- 心電図
これらの検査で異常が見つからなかった場合は、精神的なストレスや気分の落ち込みなどが、慢性的な疲労感に影響していないかどうかを見極めていきます。
慢性疲労症候群の合併症
慢性疲労症候群では、他の疾患を併発ケースも少なくありません。なかでも多く見られるのが、ストレスとの関わりが深い疾患です。
身体の病気
- 偏頭痛
- 線維筋痛症
- 過敏性腸症候群
- 機能性ディスペプシア
- 月経前症候群
- 顎関節症
心の病気
- うつ病
- 全般性不安障害
- 疼痛性障害
- 身体症状症
慢性疲労症候群の治療
漢方薬
慢性疲労症候群では、体に必要なエネルギー(=気)や栄養(=血)が十分に巡らず、不足している状態と考えられています。東洋医学では、これを「気虚」や「血虚」と呼び、その不足を補うために漢方薬(補剤)を用いることがあります。
また、消化機能の低下が慢性的な疲労が要因のこともあるため、漢方薬の選択は患者様の体質や症状に合わせて慎重に行う必要があります。
体に合わない漢方薬を服用すると、かえって体調を崩すこともあるため、自己判断での服用は避け、必ず医師に相談するようにしましょう。
- 補中益気湯(ほちゅうえっきとう)
消化機能を整え、気を補うことで体力を回復させます。気虚の基本処方です。
- 四物湯(しもつとう)
血を補い、疲れやすさや動悸、栄養不足などに用いられます。
- 加味帰脾湯(かみきひとう)
不眠や抑うつ気分が強く、消化不良もある場合に処方されます。
- 十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)
気血ともに不足しているときに、全身の消耗を回復させるために使われます。
- 人参養栄湯(にんじんようえいとう)
十全大補湯で効果が不十分なときに用いる、より強力な補剤です。
栄養療法
 準備中
準備中