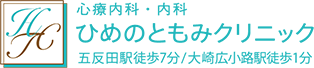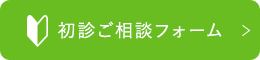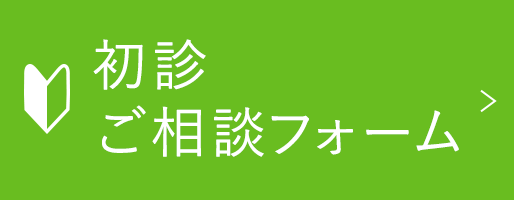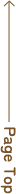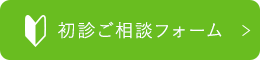発達障害とは?
 発達障害のお子さんは対人関係やコミュニケーションが難しかったり、言葉や学習に困難を感じたり、刺激や環境の変化に過敏に反応してしまうため本人も周囲の方々も日々様々な問題に直面していると思います。脳の働きや発達においてなんらかの問題が生じていると考えられています。現時点では原因が不明です。
発達障害のお子さんは対人関係やコミュニケーションが難しかったり、言葉や学習に困難を感じたり、刺激や環境の変化に過敏に反応してしまうため本人も周囲の方々も日々様々な問題に直面していると思います。脳の働きや発達においてなんらかの問題が生じていると考えられています。現時点では原因が不明です。
一般的な治療は薬や療育、周囲の環境整備によって社会生活を営めるよう助けていくことです。そのような小児精神科医や療育サポーターによる治療と並行して、私たちのクリニックでは脳の生化学という新しい視点から治療を試みています。具体的には脳の働きや発達を妨げている要因を探して取り除いていこうという試みです。
脳の働きを妨げる要因
発達障害と診断されているお子さんを調べてみると、バリア機構が弱かったり有害物質の排泄能力が低かったりすることが観察されます。消化管のバリアが弱いと大きなたんぱく質の塊が体内に入り込んで余分な免疫反応を起こします。同様のことが脳にも起きていて、本来入ってはいけない物質が侵入することによって炎症・免疫反応が起きたり神経の働きを混乱させたりします。
大気汚染物質や農薬、水銀などの有害重金属は通常であれば自然の排泄能力によって除去され大きな問題を起こしませんが、排泄能力を超えて蓄積してしまうと発達期の脳の機能障害を起こしてしまう場合もあります。便秘や腸内のカビは解毒の負担をさらに悪化させます。
バイオロジカル検査はこのような問題を見つけ出すために有用です。脳の発達を阻害している問題を一つ一つ解決することにより潜在的な能力を発揮出来るように手助けします。
大人の発達障害の特徴
発達障害は生まれつきの特性であり、成人になって突然発症するものではありません。「大人の発達障害」とは、子どもの頃には気づかれず、大人になってから診断を受けたり、自ら気づくようになったケースを指します。
発達障害は、一般的には幼少期に見つかることが多いですが、症状の現れ方には個人差があり、特に軽度の場合は周囲が気づかないまま成長することもあります。
しかし、社会に出てから仕事や人間関係に困難を感じる場面が増えると、「自分は他の人と何か違うのではないか」といった違和感や、生きづらさを覚えるようになることがあります。その結果、うつ病や不安障害、対人恐怖などの精神的な不調をきっかけに、発達障害が明らかになるケースも増えています。
「自分もそうかもしれない」と感じたときは、1人で悩まず、まずは当院までお気軽にご相談ください。
年代別の症状
| 多動 | 不注意 | 衝動性 | |
| 就学前 | 絶えず動き回る |
|
注意に向けずに行動し、危険に対する認識が乏しい |
| 小学生 | 静かにする場面でも落ち着きがない |
|
|
| 思春期 | 常にソワソワしている |
|
|
| 大人(成人) | 自分でも落ち着きのなさを自覚していることが多い |
|
|
発達障害の主な種類
広汎性発達障害(自閉スペクトラム症、ASD)
対人コミュニケーションや社会性の面で特性が見られる発達障害の1つです。相手の気持ちを読み取ることが苦手で、場の空気にうまく馴染めないことがあり、人とのやり取りがちぐはぐになることもあります。例えば、自分が話したいことだけを一方的に話してしまい、周囲を戸惑わせることがあります。その一方で、興味を持った分野については非常に詳しく、深い知識を持っていて、周囲を驚かせたり感心させたりすることも少なくありません。また、行動や考え方に一定のパターンやこだわりがあるのも特徴です。
注意欠陥多動性障害(ADHD)
集中力の欠如(不注意)、落ち着きのなさ(多動)、考えるより先に行動してしまう衝動性といった特徴が見られる発達障害です。例えば、大事な仕事の予定を忘れてしまったり、必要な資料を置き忘れるなど、周囲から「だらしない」「仕事ができない」と誤解されることがあります。一方で、新しいことに対して柔軟にチャレンジできる力や、即断即決で行動できる判断力に優れている一面もあります。
学習障害(LD)
学習障害は、知的な発達に問題がなく、視力や聴力、教育環境にも特別な問題がないにもかかわらず、「読み」「書き」「計算」など特定の学習分野だけでつまずきが見られる状態を指します。幼少期には目立たないことが多いですが、小学校に入学し、国語や算数などの教科学習が本格的に始まるタイミングで、苦手が明らかになり、周囲が気づくことが多くなります。
発達障害の検査
- 尿中有機酸検査
- マイコトキシンプロファイル
- 遅延型フードアレルギー検査
- 栄養解析検査
- GI マップ
- 体内ミネラル・有害重金属検査(年齢制限あり)
※血液検査が難しい年齢のお子さんには尿の検査だけでも多くの情報を得られます。
発達障害の診断
 発達障害の診断では、主に問診と心理検査が用いられます。問診では、ご本人やご家族と面談を行い、これまでの発達の様子や日常生活での困りごと、行動の特徴などを丁寧に伺います。
発達障害の診断では、主に問診と心理検査が用いられます。問診では、ご本人やご家族と面談を行い、これまでの発達の様子や日常生活での困りごと、行動の特徴などを丁寧に伺います。
心理検査では、認知の特性や対人関係・社会的な適応力、コミュニケーション能力などを専門的な視点で評価します。
これらの情報をもとに、医師や心理士などの専門家が総合的に判断を行い、診断がつけられます。
診断は単なるラベル付けではなく、その人に合った支援や治療を見つけるための大切な手がかりになります。
発達障害の治療
お一人お一人のお子さんの特性や問題点に合わせてアプローチを個別に組み立てます。中心になるのは食事の改善で、除去食が必要になる場合もあります。便通を整えること、よい栄養を摂ること、害のある食品成分を摂らないようにすることが重要です。サプリメントは最低限を心掛けていますが早期の改善のためにサプリメントが必要になることもあります。