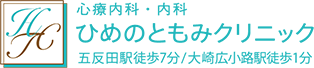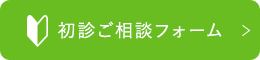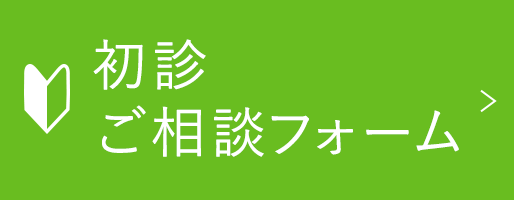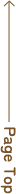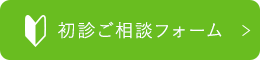糖尿病とは
 糖尿病は、ブドウ糖(血糖)がうまく細胞に取り込まれなくなり、血液中の血糖値が慢性的に高くなる疾患です。
糖尿病は、ブドウ糖(血糖)がうまく細胞に取り込まれなくなり、血液中の血糖値が慢性的に高くなる疾患です。
このような高血糖の状態が長く続くと、全身の血管が傷つき、様々な合併症を引き起こす原因となります。
そのため、糖尿病と診断された場合は、血糖値を適切に管理し、合併症の予防に努めることが重要です。
糖尿病の種類・原因
糖尿病は主に1型糖尿病と2型糖尿病に分類され、日本では患者の95%以上が2型糖尿病です。
2型糖尿病
2型糖尿病の症状
2型糖尿病は、初期の段階ではほとんど自覚症状がなく、気づきにくいのが特徴です。しかし、合併症が進行すると、全身に様々な症状が現れるようになります。代表的な合併症の症状は以下のとおりです。
- 手足の感覚が鈍くなる、あるいはチクチクと刺すような痛みを感じる
- 傷や皮膚の切り傷が治りにくくなる
- 頻繁に尿意を感じる(頻尿)
- 感染症にかかりやすくなる
- 勃起不全(ED)など性機能に関する問題が起こる
2型糖尿病の原因
2型糖尿病は、インスリンの分泌量が減少したり、「インスリン抵抗性」と呼ばれるインスリンの働きが悪くなる状態が引き金となって発症します。その背景には、以下のような複数の要因が関わっています。
- 加齢(特に40歳以上で発症リスクが高まります)
- 運動不足
- 過食、早食い、一度に大量に食べる習慣
- 肥満
- 不規則な食事のタイミング
- 過度なストレス
- 遺伝的な体質
1型糖尿病
1型糖尿病の症状
1型糖尿病は、症状が急に現れることが多く、急性の合併症を引き起こすのが特徴です。
進行すると、呼吸困難や吐き気・嘔吐を伴い、重篤な場合は昏睡状態に陥るなど、命に関わる危険な状態に至ることもあります。
主な症状は以下のとおりです。
- 以前より喉の渇きを強く感じるようになる
- 急激に体重が減少する
- 頻繁に尿意を感じる(頻尿)
- 強い疲労感が続く
1型糖尿病の原因
1型糖尿病は、膵臓にあるインスリンをつくる「β細胞」が何らかの原因で破壊され、インスリンの分泌量が著しく低下することで発症します。その結果、血糖値が高くなり、糖尿病の症状が現れます。
治療には、体外からインスリンを補う「インスリン療法」が基本となります。
糖尿病の症状
糖尿病の大きな特徴の一つは、初期にはまったく症状が現れないことです。そのため、病気が進行していても自覚しにくく、発見や治療の開始が遅れるケースが少なくありません。
このような性質から、糖尿病は「サイレント・キラー」とも呼ばれ、自覚のないまま身体に深刻なダメージを与える危険な疾患とされています。
糖尿病が進行すると、若い世代であっても心筋梗塞や脳梗塞といった合併症を引き起こし、寿命が約10年短くなる可能性もあります。
実際、糖尿病患者の平均寿命は以下のように報告されています。
- 男性:約69歳
- 女性:約72歳
糖尿病の合併症
動脈硬化(脳卒中・心臓病)
糖尿病における代表的な合併症の一つが動脈硬化です。
動脈が硬くなると、心臓病や脳卒中を引き起こすリスクが高まります。特に、食後の急激な血糖値の上昇は動脈硬化を進行させやすく、注意が必要です。
その進行を抑えるためには、糖尿病だけでなく、以下のような関連疾患の管理も重要となります。
- 高血圧
- 脂質異常症
- 肥満
糖尿病網膜症
目の内側には網膜という膜状の組織があり、光や色を感じ取る神経細胞が並んでいます。
高血糖状態が長期間続くと、網膜にある細い血管が損傷を受け、血流が悪化します。その結果、酸素や栄養が行き届かなくなり、視力が低下していきます。
糖尿病神経障害
高血糖によって神経に栄養を届ける血管が動脈硬化を起こし、神経がダメージを受けます。特に末端にいくほど血管が細くなるため、足先などでは血流が届きにくくなり、以下のような症状が見られます。
- 足先のしびれ
- 冷え
- 感覚の低下
糖尿病腎症
高血糖状態が続くと腎臓の血管にもダメージが及び、老廃物を体外に排出する機能が低下します。その結果、以下のような症状が現れます。
- 尿にタンパクが漏れる(タンパク尿)
- むくみ
- 腎機能の悪化
腎機能の維持には、血糖コントロールに加え、血圧や水分の管理など、様々な生活習慣の見直しが必要です。
糖尿病足病変
神経障害により足先の感覚が鈍くなり、末梢動脈の血流障害、高血糖による免疫力低下も重なることで、足に感染症が起きやすくなります。
さらに、視力低下により足の傷に気づきにくくなると、傷が悪化し、次のような深刻な状態に進行することもあります。
- 潰瘍(かいよう)
- 壊疽(えそ)
認知症
高血糖により脳の血管が障害を受けると、脳梗塞を原因とする認知症だけでなく、アルツハイマー型認知症の発症リスクも高まることが分かっています。
HbA1cの値が上昇するほど、認知機能が低下しやすいというデータもあります。
糖尿病の治療

糖尿病の治療は、以下の3つの方法を組み合わせて行います。
- 食事療法
- 運動療法
- 薬物療法(内服薬やインスリン注射など)
当院では特に食事療法に力を入れていて、極力薬を使わないで改善を試みたり、現在飲んでいる薬を減らしたり出来ることを目指しています。ただし、糖尿病の原因も治療の効果も一人一人異なりますので、あくまでもその方に合わせた適切な治療を選択し、快適に継続していただくことによって、血糖値を安定させて症状の進行や合併症を防ぐことを目標とします。
治療の目標となる数値
糖尿病治療では平均的な血糖値を反映する「HbA1c(ヘモグロビンA1c)」を指標とすることが多いのですが、同じHbA1cでも血糖値スパイクの有無が合併症の起こしやすさに関係します。血糖値を下げることだけでなく血糖変動を少なくすることを目標とします。
食事療法
糖尿病治療の中心となるのは、血糖値のコントロールです。血糖値を急激に上昇させない食事の仕方を学び実践していただきます。
低糖質を中心とした食事療法
同じカロリーでも血糖値の上がり方は食品によって違います。特に2型糖尿病はインスリンが過剰に刺激され続けた結果、内臓脂肪が増えてインスリンの効き目が悪くなっている方が大部分です。したがって血糖値を上げない食事、インスリンの過剰な分泌を刺激しない食事をすることが重要です。必要な穀物摂取量を確保した上で、消化吸収のゆっくりした食材を選び、食べる順番など血糖変動を穏やかにする工夫を指導いたします。
1日3食、規則正しい食習慣を
食事をとると血糖値は自然に上がりますが、不規則な時間に食事をとったり、1日1〜2食しか食べないと、血糖値の変動が不安定になり、膵臓への負担が大きくなります。
- 1日3食、できるだけ同じ時間に食事をとる
- 1食あたりの量を均等に分ける
- ゆっくり噛んで食べることで血糖値の急上昇を抑える
良質のたんぱく質と脂質を摂るカロリー制限食では食事摂取量、特に動物性たんぱく質が不足しがちになります。合併症の予防やエネルギー代謝の活性化のために、健常者よりも多くのたんぱく質やビタミン、ミネラル、必須脂肪酸などの必須栄養素を摂る必要があります。動物性たんぱく質にはこれらの栄養素が豊富に含まれています。特にω3系脂肪酸やミネラルを多く含む魚介類は積極的に摂って欲しい食品です。当院では、必須栄養素という観点から、一日に必要な食品の種類や量を丁寧にご説明いたします。
運動療法
運動をするとインスリンを使わずにぶどう糖を筋肉に取り込むことが出来ます。筋肉が増えると基礎代謝があがりますし、空腹時にアミノ酸から糖を作り出す機構が働きやすくなり血糖値の安定につながります。摂取カロリー量や体重、合併症の有無などによって適切な運動の強度や種類を選んで行いましょう。
運動療法の注意点
- 急に激しい運動をすると危険です。まずは軽めの運動から始め、少しずつ強度や時間を増やしていきましょう。
- 血糖値を下げる観点からは食後の運動や筋トレがお勧めです。
- 短時間でも効果はあります。継続しやすく、楽しめる運動を選ぶことがポイントです
- 必要に応じて、運動前後の血糖値のチェックを行いましょう
「HbA1cや血糖値が高い」と
言われた方は当院へ
 糖尿病は初期段階では自覚症状がほとんどありませんが、放置すると血糖値が上昇し、合併症を引き起こす可能性があります。そのため、早期に適切な治療を受けることが非常に重要です。
糖尿病は初期段階では自覚症状がほとんどありませんが、放置すると血糖値が上昇し、合併症を引き起こす可能性があります。そのため、早期に適切な治療を受けることが非常に重要です。
当院では、五反田駅周辺をはじめ、品川区大崎、小山、不動前駅周辺にお住まいの方々にも糖尿病の診察や検査、治療を行っています。
少しでも気になる症状がある方、血糖値が高い方、検診などでHbA1cが高いと言われた方、またご家族に糖尿病治療中の方がいらっしゃる場合は、どうぞお気軽に当院までご相談ください。