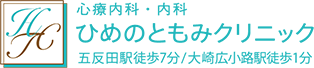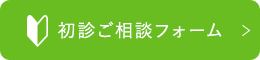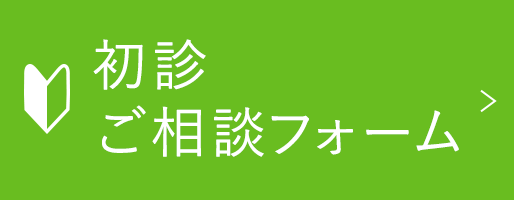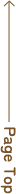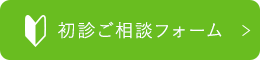過敏性腸症候群の症状

- 腹痛
- 腹部の不快感
- 便秘・下痢を繰り返す
- ガスの頻発
- 吐き気
なお、腹痛や便秘・下痢などの症状の原因となる疾患は多岐にわたります。これらの症状にお悩みの方は、原因を特定するために当院までご相談ください。
過敏性腸症候群とは
過敏性腸症候群(IBS)は、小腸や大腸に潰瘍や腫瘍といった異常が見つからないにもかかわらず、腹痛や腹部の張り、便秘・下痢などの症状が慢性的に現れる疾患です。
腸が必要以上に敏感になっており、ストレスや緊張などの刺激に反応しやすくなることで、腸の動きが乱れてしまうと考えられています。
日本における有病率はおよそ10〜20%と言われており、特に現代のようにストレスの多い社会環境の中では、悩む方が増えてきています。
下痢型
急に強い便意を感じて何度もトイレに駆け込まなければならないような下痢の症状が特徴です。
便は水のように柔らかいことや、粘液を含んでいることもあります。
便秘型
お腹の張りや痛みを感じながら、なかなか便が出ない状態が繰り返されるのが特徴です。
便はコロコロとして硬く、水分が少ないため排便時に強い不快感を伴うこともあります。
混合型
便秘と下痢の症状が交互に現れるのが特徴で、腸の状態が日によって大きく変動します。
ストレスや緊張などの心理的要因に強く影響されやすいです。
分類不能型(ガス型)
便秘型・下痢型・混合型のいずれにも当てはまらないタイプです。
頻繁におならが出る、腹部の張りや膨満感が続くといったケースがあり、これらは「ガス型」と呼ばれることもあります。
過敏性腸症候群の原因
過敏性腸症候群の発症には、自律神経の乱れが深く関わっていると考えられています。
腸の働きは自律神経によって調整されており、食事を摂ると、胃・小腸・大腸へと食べ物が運ばれ、消化吸収された後、不要なものが腸の運動によって直腸へ送られることで排便が行われます。しかし、緊張や不安などのストレスによって自律神経のバランスが崩れると、腸が過敏に反応して痙攣を起こし、排便のリズムが乱れます。その結果、腹痛や便秘・下痢といった症状が現れるのです。
また、一度過敏性腸症候群を経験すると「また症状が出たらどうしよう」という不安がストレスを助長し、さらに症状を引き起こすという悪循環に陥るケースも少なくありません。
なお、原因はストレスだけに限られず、偏った食事や不規則な睡眠といった生活習慣の乱れも、腸の働きに悪影響を及ぼします。
過敏性腸症候群の治し方
 過敏性腸症候群の治療では、生活習慣を整えることが大きなポイントになります。
過敏性腸症候群の治療では、生活習慣を整えることが大きなポイントになります。
治療は食事療法と薬物療法が基本となり、必要に応じて心理療法も取り入れられます。
便秘薬や下痢止めを自己判断で使用するケースも見られますが、症状や体質に合っていないと逆効果になることもあるため注意が必要です。副作用のリスクもあるため、医師の判断のもとで適切な治療を受けることが大切です。
つらい症状が続く場合は、早めに当院までご相談ください。
薬物療法
過敏性腸症候群の治療では、症状のタイプに応じて様々なお薬が使われます。
腸の動きを整えるお薬や、腸内環境を改善する整腸剤(プロバイオティクス)、腹痛を和らげるお薬、下痢や便秘に対する対症薬などが一般的です。
また、ストレスや不安が影響しているケースでは、抗不安薬や自律神経のバランスを整えるお薬、さらには漢方薬が処方されることもあります。
心理療法
過敏性腸症候群は、ストレスの影響を大きく受ける病気です。そのため、お薬だけではなかなか改善しない場合には、心のケアも併せて行うことが効果的です。
ストレスへの対処法を学ぶ「ストレスマネジメント」や、心身を落ち着ける「リラクゼーション療法」などを取り入れることで、症状の緩和が期待できます。
過敏性腸症候群の食べ物
- 1日3食を規則正しく摂り、栄養バランスの良い食事を心がけながら、暴飲暴食や就寝前の食事は控えるようにしましょう。
- 脂っこい料理や香辛料、コーヒー、炭酸飲料、アルコールなどの刺激の強いものは腸を刺激しやすいため、控えるようにしましょう。
- 一度にたくさん食べるのではなく、少量を回数に分けて、落ち着いて食事をすることが大切です。
- お腹の張りやガスが気になる方は、豆類やキャベツなどの消化に時間がかかる食材は避けたほうが良いでしょう。
- 「FODMAP」と呼ばれる発酵性糖質を多く含む食品は腸内でガスを発生させやすいため、これらの摂取を控えると症状が和らぐことがあります。
- 便秘型の方は食物繊維を積極的に摂るようにし、下痢がある方は消化に優しい食材を選ぶことが大切です。
- 症状に合わせて、低脂肪食や低FODMAP食、食物繊維の量を調整するなど、個人の体調に合わせた食事の工夫を取り入れましょう。