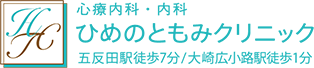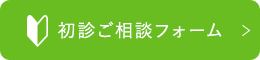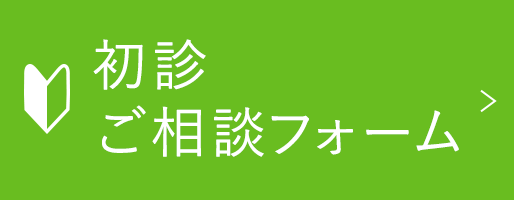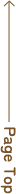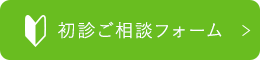原因不明の体調不良
「不定愁訴」とは
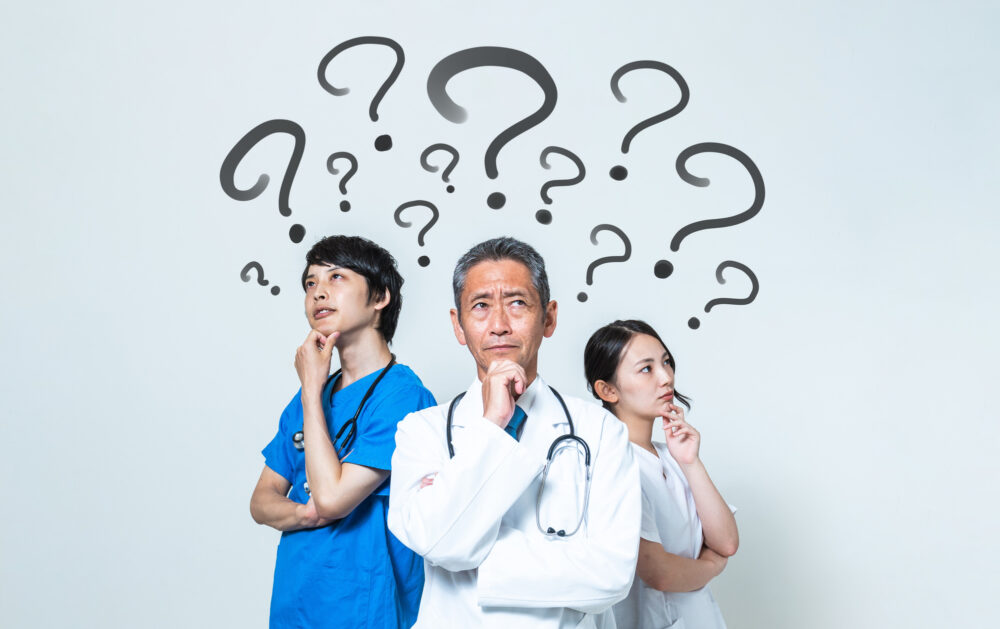 不定愁訴(ふていしゅうそ)とは、検査では異常が見つからないにもかかわらず、体に様々な不調を感じる状態を指す医療用語です。
不定愁訴(ふていしゅうそ)とは、検査では異常が見つからないにもかかわらず、体に様々な不調を感じる状態を指す医療用語です。
英語では「unidentified complaints」と表され、「原因がはっきりしない訴え」という意味になります。
本人はたしかに不調を感じているのに、医療機関でも原因が特定できず、周囲にも理解されにくいという点が、不定愁訴のつらさの1つです。
「病気じゃないと言われたから我慢するしかない」「原因が分からないから相談しにくい」と悩んでいる方も多く、症状を抱え込んでしまいがちです。
不定愁訴の症状チェック
不定愁訴では主に以下のような症状が現れます。
- 倦怠感
- 肩こり
- 頭痛
- 腹痛
- 便秘
- 下痢
- 耳鳴り
- むくみ
- 痺れ
- のぼせ
- 冷え
- 動悸
- 息切れ
- めまい
- ふらつき
- 不眠
- イライラ
- 気分の落ち込み
不定愁訴に現れる症状は人によって異なり、その現れ方も様々です。
例えば、ある人は1つの症状が長期間続くこともあれば、複数の不調が同時に現れるケースもあります。また、症状が入れ替わるように変化しながら現れるという人もいます。
不定愁訴の原因
不定愁訴は、検査では異常が見つからないにもかかわらず、体や心に不調を感じる状態を指します。そのため、はっきりとした原因は特定されていませんが、いくつか考えられている要因があります。
自律神経の乱れ
自律神経は、内臓の働きや血流、体温調整、代謝など、生命活動をコントロールしている大切な神経です。また、体だけでなく、心のバランスを整える役割も担っています。
自律神経には、活動を促す「交感神経」と、体をリラックスさせる「副交感神経」があり、この2つのバランスが保たれることで、心身の調和が保たれています。しかし、このバランスが崩れると、様々な不調が起こりやすくなります。
自律神経の乱れは、心拍数や血圧の変化などから検査できる場合もありますが、一般的な検査で確実に判断するのは難しいとされています。自律神経の乱れがあったとしても、その原因までは検査だけでは特定できないからです。
自律神経の働きは、生活習慣、ホルモンバランス、ストレス、心の状態など様々な要因に左右されるため、診断や治療には全体的な視点が必要となります。
こうした背景から、自律神経の乱れが「原因不明の体調不良=不定愁訴」として現れることも少なくありません。
疾患によるもの
不定愁訴の中には、何らかの疾患が原因となっている場合もあります。例えば、強い肩こりに悩んで整形外科を受診しても異常が見つからず、症状が改善しないケースでは、実は心の不調が関係していたということも少なくありません。
医師から「特に異常はない」と言われると、「もう少し様子を見よう」「自分の気のせいかもしれない」と我慢してしまう方も多いのが現状です。ですが、不調の陰に思いがけない疾患が隠れていることもあるため、安易に自己判断せず、必要に応じて他の診療科や専門医の意見を聞くことも大切です。
PMS(月経前症候群)
PMS(月経前症候群)は、月経が始まるおよそ3〜10日前から心や体に様々な不調が現れる症状のことを言います。原因はまだはっきりとは解明されていませんが、ホルモンバランスの変化が関係していると考えられています。
症状には個人差があり、例えば、下腹部の痛みや頭痛、めまい、動悸といった身体の不調のほか、不安感、疲労感、無気力などの心の不調が起こることもあります。
更年期障害
更年期障害は、閉経を挟んだ約10年間にわたって現れる、心や体の様々な不調の総称です。
日本人女性の閉経の平均年齢はおよそ55歳とされており、一般的には45〜55歳頃の女性に多く見られる傾向があります。
顔のほてりやのぼせ、急な発汗、動悸といった身体的な変化のほか、気分が落ち込みやすくなる、イライラしやすい、涙もろくなるといった精神的な不調も起こりやすくなります。
鉄欠乏性貧血
鉄欠乏性貧血は、体内の鉄分が不足することで発症する貧血の一種です。
主な症状としては、動悸、息切れ、めまい、立ちくらみ、慢性的な疲労感などが挙げられます。
特に、月経のある女性は鉄分を失いやすいため、鉄欠乏性貧血になりやすい傾向があります。なかでも、月経の量が多い過多月経などが原因となっていることも多いです。
子宮や卵巣の疾患
子宮筋腫や子宮内膜症、卵巣腫瘍など、子宮や卵巣に関わる疾患がホルモンバランスの乱れを引き起こし、様々な不調を招くことがあります。
こうした病気が関係している場合、頭痛や慢性的な疲労感、だるさ、肩こり、腰の痛みといった症状が現れやすいと言われています。
不定愁訴の対策・治療
以下では、つらさを少しでも和らげるために日常生活の中で取り入れやすい対処法をご紹介します。
食生活の改善
不定愁訴の対策として、毎日の食事を見直すこともとても大切です。
タンパク質・炭水化物・脂質・ミネラル・ビタミンなど、体に必要な栄養素をバランス良く摂ることで、体調の安定や不調の改善に繋がります。人によって体の状態や必要な栄養は異なるため、自分に合った食事を意識していくことがポイントです。
生活習慣の改善
夜更かしが続いたり、食事を抜いてしまったりと、不規則な生活が続くと自律神経のバランスが乱れやすくなります。まずは、早寝早起きやこまめな休息、規則正しい食事など、基本的な生活習慣を整えることから始めてみましょう。
ストレスの発散
仕事や人間関係など、日々のストレスが積み重なると、自律神経のバランスが崩れ、不調の原因になることもあります。そのため、意識的にストレスを発散する時間を作ることが、不定愁訴の予防や緩和にも繋がります。
運動習慣
体を動かすことは、ストレスの解消や血流の促進、食欲の改善、そして睡眠の質を高める効果が期待できます。さらに、運動は自律神経のバランスを整える働きもあると言われており、不定愁訴の対策としても有効です。ウォーキングや軽いジョギング、水泳など、続けやすい運動を自分のペースで取り入れてみましょう。
原因不明の体調不良は当院へ
 検査では異常が見つからず、周囲の理解も得にくいのが不定愁訴の特徴です。
検査では異常が見つからず、周囲の理解も得にくいのが不定愁訴の特徴です。
「どこも悪くないのに、このつらさは気のせいなのかな」と無理を続けてしまうと、心や体にさらに負担がかかり、深刻な症状に繋がる恐れもあります。
どこに行ってもはっきりした原因が見つからない、理解されないと、不調を抱える方は、ひめのともみクリニックにご相談ください。
当院では、まずは丁寧に症状をお伺いし、つらさに寄り添うことを大切にしています。
「分かってくれる人がいる」と感じられるだけでも、心の重荷が少し軽くなり、それが回復への第一歩になることもあります。