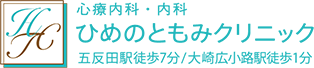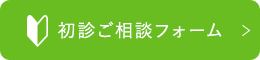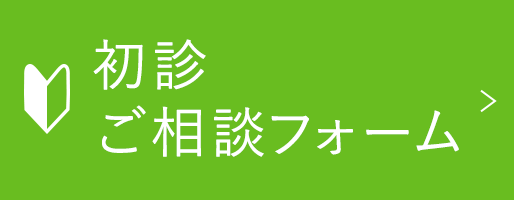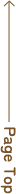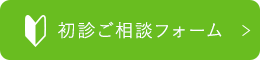強迫性障害とは

強迫性障害は、自分の意思とは関係なく頭に浮かんでしまう「強迫観念」と、その不安を振り払うために繰り返される「強迫行為」が特徴の精神疾患です。
例えば、「手が汚れているのではないか」「鍵をかけ忘れたのではないか」といった不安な考えが繰り返し浮かび(強迫観念)、それを打ち消そうとして何度も手を洗ったり、鍵を確認したりする行動(強迫行為)を繰り返してしまいます。
本人は「やりすぎかもしれない」「不合理だ」と分かっていても、不安が強く、どうしても行動を止めることができないのが特徴です。そのため、生活や仕事、人間関係に大きな支障をきたすことも少なくありません。
また、うつ病やパニック障害、社会不安障害など、他の不安障害と併発するケースも多く認められます。
強迫性障害の症状
強迫性障害の代表的な例としては、次のようなものがあります。
不潔恐怖・洗手強迫
- 手すりやドアノブ、電車のつり革などが不潔に感じられ、触れることができない
- 汚れやウイルスに感染することへの強い恐怖から、必要以上に手洗いや入浴を繰り返す
確認行為

- 玄関の戸締りや鍵がきちんと閉まっているか、何度も確認する
- ガスの元栓や電気のスイッチなどを消し忘れていないか、何度も確認する
加害恐怖
加害恐怖とは、自分が意図せず他人に危害を加えてしまったのではないかという不安が頭から離れず、強い恐怖を感じてしまう状態です。具体的には、次のような思考や行動が見られます。
「歩いているときに、誰かにぶつかってしまったのではないか」
「運転中に、何かに接触してしまったのではないか」
こうした不安が消えず、他人に何度も確認したり、警察に連絡して被害届が出ていないかを繰り返し確認するといった行動に繋がることもあります。
強迫儀式
強迫儀式とは、「物事は自分の決めた順番や方法で行わなければならない」という強いこだわりから、一定の手順を繰り返さずにはいられなくなる状態です。
物事へのこだわり
- 家具やリモコンなどの小物の位置に過剰にこだわり、常に決まった場所に置かれていないと落ち着かない
- 物が少しでも曲がっていたり、位置が変わっていた場合には、必ず元の場所に戻さないと気が済まない
強迫性障害の症状は、玄関の鍵を何度も確認したり、手を繰り返し洗ったりといった、誰もが日常生活の中で経験する気になる行動の延長線上にあることがほとんどです。しかし、こうした行動がエスカレートして重症化すると、治療による改善が難しくなることがあり、場合によっては自殺のリスクが高まるという報告もあります。
もし、強迫観念や強迫行為によって日常生活や社会生活に支障が出ている、または家族や周囲の人が対応に困っているといった兆しが見られる場合には、早めに当院までご相談ください。
強迫性障害になりやすい人
強迫性障害は、もともと「強迫的性格」と呼ばれる傾向を持つ人に起こりやすいとされています。強迫的性格とは、以下のような特徴を指します。
- 柔軟性や適応力に欠ける
- 堅苦しい
- 几帳面で細かいことまで気になる
- 完璧主義で、妥協ができない
- 秩序や規律を強く好む
- 小さなことにも過剰にこだわる
- 決断に時間がかかる
こうした性格傾向を持つ人は、日常生活の中でストレスを受けやすく、強迫性障害だけでなく、様々な心身の不調を引き起こすリスクが高いとされています。
強迫性障害の原因
強迫性障害の原因は、現時点ではまだ明確に解明されていません。ただし、脳の働きに関わる神経学的な要因や、育った環境・日常のストレスなど、様々な要素が関係している可能性があるとされ、現在も研究が進められています。
神経要因
強迫性障害の発症には、脳内の神経伝達物質であるセロトニンの働きが関係している可能性があると指摘されています。なお、現時点ではその仕組みについてはまだはっきりと分かっていません。
環境要因
強迫性障害は、ストレスや生活環境の変化など、外的な要因が影響して発症することが多いとされています。特に女性の場合は、月経前や出産後など、ホルモンバランスが大きく変化する時期に症状が現れやすいといわれています。
また、心に大きな衝撃を受けるようなトラウマ体験の後に発症するケースも報告されており、心理的なダメージが引き金となることも少なくありません。
強迫性障害の治療
 強迫性障害の治療は、主に薬物療法と心理療法の2つを軸に進めていきます。
強迫性障害の治療は、主に薬物療法と心理療法の2つを軸に進めていきます。
薬物療法では、不安や恐怖などの精神的・身体的な症状を軽減するために、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)がよく使用されます。症状が重度の場合は、非定型抗精神薬や気分安定薬を使用することもあります。
症状が落ち着いてきた段階で取り入れられるのが心理療法です。中心となるのは認知行動療法で、物事の捉え方や思考の偏りに気づき、それを行動に結びつけて少しずつ修正していくことで、不安にとらわれにくい考え方を身につけていきます。