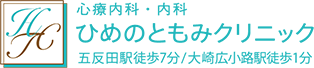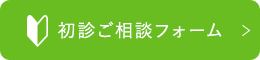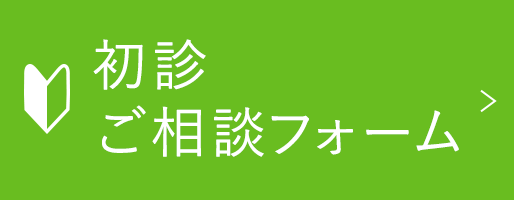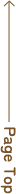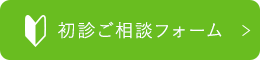- 起立性調節障害とは?中学生に多い?
- 起立性調節障害の症状
- 起立性調節障害の原因とタイプ
- 起立性調節障害の診断
- 起立性調節障害の治し方
- 保護者の方へ
- 起立性調節障害はご相談ください
- 当院のアプローチ:オーソモレキュラー栄養療法によるサポート
起立性調節障害とは?
中学生に多い?
起立性調節障害(OD:Orthostatic Dysregulation)は、自律神経のバランスが乱れることで、朝起きられない・立ちくらみ・だるさ・頭痛などの症状が出る病気です。特に10代の子どもや思春期の時期に多く見られます。
この病気は自分の意思ではどうにもならない体の不調によって、学校に行けなかったり、生活に支障が出たりします。怠けているわけではなく、体の機能がうまく働かないことが原因です。
起立性調節障害の症状
起立性調節障害の症状は、特に午前中に強く出るのが特徴です。
- 朝なかなか起きられない
- 朝は動けないのに、午後や夕方には元気になる
- 立ち上がると、めまいやふらつきがある
- 頭痛・吐き気・腹痛・動悸
- 疲れやすく、学校に行きたくても行けない
- 集中力の低下やイライラ感
- 食欲の低下や不眠
症状には波があり、「元気な日もあれば、何もできない日もある」という状態を繰り返します。
起立性調節障害の
原因とタイプ
起立性調節障害は、以下のような要因が複雑に関係しています。
起立性調節障害の原因
- 思春期の急激な成長:体の大きさに対して自律神経の発達が追いつかない
- ストレスや精神的な負担:進学、人間関係、家庭内の問題など
- 不規則な生活習慣:夜更かし、朝食抜き、スマホの使いすぎなど
- 体質:低血圧傾向の人に多い
起立性調節障害の主なタイプ(診断上の分類)
- 起立直後性低血圧型:立ち上がるとすぐに血圧が下がる
- 体位性頻脈症候群(POTS):立ち上がると心拍数が急に増える
- 神経調節性失神型:長時間立っていると失神してしまう
- 遷延性起立性低血圧型:立ってしばらくすると血圧が下がる
タイプによって症状の出方や治療方針が少しずつ異なります。
起立性調節障害の診断
起立性調節障害は、問診と検査をもとに診断します。
主な診断方法
詳しい問診・生活状況の聞き取り
以下の11項目のうち3つ以上当てはまる場合は、起立性調節障害が疑われます。
- 立ちくらみ、あるいはめまいを起こしやすい
- 立っていると気持悪くなる、ひどくなると倒れる
- 入浴時あるいは嫌な事を見聞きすると気持ちが悪くなる。
- 少し動くと動悸あるいは息切れがする。
- 朝なかなか起きられず午前中は調子が悪い
- 顔色が青白い
- 食欲不振
- へその周りが時々痛い
- だるい。あるいは疲れやすい。
- 頭痛
- 乗り物に酔いやすい
起立試験(新起立試験)
横になった状態から立ち上がり、血圧や脈拍の変化を測定します
その他
必要に応じて、血液検査や心電図などを行う場合もあります
当クリニックでは、お子さまの生活背景や心理面のサポートも含めた丁寧な診察を行っています。
起立性調節障害の治し方
治療は生活習慣の見直しが基本になりますが、必要に応じて薬の使用や心理的サポートも行います。
生活習慣の見直し

- 朝食をしっかりとる(塩分・水分も大切)
- 就寝・起床のリズムを整える
- 適度な運動(ストレッチや軽い散歩)
- 長時間のスマホやゲームを控える
- 体を締めつけない服装や、朝の光を浴びる習慣も効果的です
薬物療法
- 血圧を調整する薬(ミドドリンなど)
- 漢方薬(五苓散、半夏白朮天麻湯、苓桂朮甘湯など)
- 頭痛や胃腸症状への対症療法
※薬は症状や年齢に応じて慎重に処方します。
心理的サポート
- 「怠けているのではなく、病気であること」の理解
- 学校や家族との関係調整
- 必要に応じて、カウンセリングやスクールカウンセラーとの連携も行います
保護者の方へ
起立性調節障害は、体の機能の不調によって引き起こされる病気です。子ども自身も「行きたいのに行けない」というつらさを感じています。
「甘え」や「怠け」と決めつけるのではなく、まずは体の状態を理解し、必要なサポートをすることが大切です。早期に適切な対応をすれば、多くの子どもたちは回復し、学校生活にも復帰できます。
起立性調節障害は
ご相談ください
当クリニックでは、起立性調節障害の診断・治療に対応しています。お子さまやご家族が不安を感じている場合は、どうぞお気軽にご相談ください。医師・看護師・栄養士・スタッフがチームでサポートいたします。
当院のアプローチ:
オーソモレキュラー栄養療法
によるサポート
当院では、起立性調節障害の治療において、「オーソモレキュラー栄養療法(分子整合栄養医学)」を積極的に取り入れています。
オーソモレキュラー療法とは、体に必要な栄養素(ビタミン・ミネラル・アミノ酸など)を医学的な視点で適切に補い、体の機能を根本から整えていく治療法です。
なぜ、栄養療法が効果的なのか?
起立性調節障害は、自律神経の働きの乱れが原因ですが、その背景には以下のような**「体の栄養状態のアンバランス」**が関係していることも少なくありません。
- 朝食欠食や偏食、夜型生活による栄養不足
- ストレスや思春期による亜鉛やビタミンB群の消耗
- 貧血傾向(鉄・たんぱく質不足)や低血糖傾向
- 自律神経を支えるミネラル(マグネシウム、ナトリウム)の不足
これらを見落としたままでは、薬だけではなかなか改善しないこともあります。
具体的な取り組み
当院では、以下のような流れでオーソモレキュラー栄養療法を導入しています。
- 詳細な問診・食生活の確認
- 必要に応じた血液検査(一般検査+栄養指標)
- 個別の栄養補給プランの作成
- 食事指導
また、栄養補給だけでなく、心身のバランスを整える生活アドバイスも併せて行い、回復へのスピードアップを図ります。
オーソモレキュラー療法を取り入れることで期待できること
- 朝の目覚めやすさの改善
- 午前中の活動量の向上
- 頭痛やだるさなどの軽減
- 気持ちの安定、意欲の回復
- 長期的に体調を崩しにくい体づくり
薬だけに頼らない、「体の中から整えるアプローチ」として、多くの患者さんにご好評をいただいています。
医師・スタッフの専門資格と実績
当院では、医師がオーソモレキュラー栄養療法を専門的に学び、臨床経験に基づいた診療を行っています。
姫野医師
- 日本オーソモレキュラー医学会理事
- 一般内科・心療内科医として40年以上の診療経験
- 思春期の心身症・発達特性への対応にも精通
栄養スタッフ(管理栄養士・栄養カウンセラー)
- 分子栄養学を学び、個別に栄養指導を実施
- お子さま・保護者と丁寧に寄り添うサポート体制
当院では、医学的根拠に基づいた栄養療法を通じて、「体と心の両面から整える医療」を提供しています。
ご相談・初診予約はこちらから
「うちの子もそうかもしれない…」「薬に頼らない方法を知りたい」
そんな方は、どうぞお気軽にご相談ください。
初診では、症状や生活背景をじっくり伺い、必要な検査や治療のご提案をいたします。