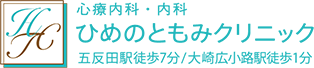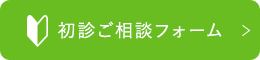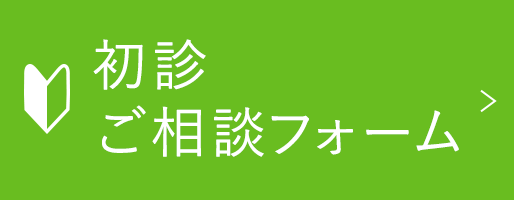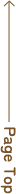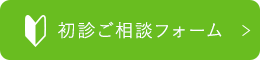睡眠障害とは

睡眠障害とは、眠りに関する様々なトラブルを指します。例えば、「なかなか眠れない」「途中で目が覚めてしまう」「逆に眠りすぎてしまう」「寝る時間と起きる時間がどんどんずれてしまう」など、症状の現れ方は人それぞれです。
原因も多岐にわたりますが、症状に合わせた適切な治療や生活改善によって、少しずつ改善を目指すことができます。睡眠についてお悩みの方は、当院までお気軽にご相談ください。
睡眠障害の原因はストレス?
睡眠障害の原因は1つではなく、様々な要素が関係しています。例えば、加齢や生活習慣病などの身体的な要因、ストレスや気分の落ち込みなどの精神的な要因、さらにはお薬の副作用や寝室の光・音など環境の影響も関わってきます。
最近では、就寝前にスマートフォンやパソコンなどの画面を長時間見続けることによって神経が刺激され、脳が興奮して眠りにくくなるケースも増えています。
当院では、こうした様々な要因の中から患者様にとっての原因を見極め、適切な治療やアドバイスを行っています。
睡眠障害の種類
不眠症
不眠症は、現代では「国民病」とも言われるほど多くの人が悩んでいる睡眠の問題です。ある調査では、成人の3~4割が何らかの不眠の症状を感じているという結果も出ています。
不眠の症状は様々で、例えば「寝つきが悪い」「夜中に何度も目が覚めてしまう」「朝早く目が覚めてそのまま眠れなくなる」「ぐっすり眠った感じがしない」など、入眠障害、中途覚醒、早朝覚醒、熟眠障害といった4つの種類があります。
必要な睡眠時間は個人差がありますが、睡眠が十分に取れないことで、日中に強い眠気や集中力の低下などの支障が出る場合には、「不眠症」と診断されることがあります。
過眠症
過眠症は、十分な時間眠っているにもかかわらず、日中にも強い眠気を感じてしまう病気です。例えば、朝起きられずに学校や会社に遅れてしまったり、日中の活動に支障をきたしてしまったりといった問題が起こります。
「たっぷり眠ったはずなのに眠い」という状態には、実は眠りの質が浅くなっている場合や、脳の機能に何らかの異常があることが原因として考えられます。
慢性的な眠気に悩んでいる方は、一度当院までご相談ください。
睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群は、眠っている間に呼吸が何度も止まってしまう疾患です。
主な原因としては、仰向けに寝ることで気道が塞がれてしまうタイプと、脳の呼吸をコントロールする機能に異常があるタイプの2つがあります。いずれの場合も、呼吸が一時的に止まることで眠りが浅くなり、心臓や身体全体に大きな負担がかかるため、早めの対処が大切です。
むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)
むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)は、眠ろうとして横になるときに脚にむずむずする不快感や、かゆみ・痛みのような感覚が現れて眠れなくなる症状が特徴です。
この症状は、脳内の神経伝達物質「ドーパミン」の働きが関係していると考えられていますが、現時点でははっきりとした原因は特定されていません。
原因が特に見当たらない「特発性」と、鉄欠乏性貧血などの疾患が背景にある「二次性タイプ」に分けられ、それぞれで対応が異なります。
周期性四肢運動障害
周期性四肢運動障害は、睡眠中に手や足がピクピクと痙攣するように動いてしまう病気です。これらの動きは自分の意思とは関係なく起こり、眠りを浅くしたり、途中で目が覚めてしまったりする原因になります。
多くの場合、本人はこうした動きに気づいていないことが多く、むずむず脚症候群と一緒に見られることもよくあります。
睡眠中の異常行動・レム睡眠行動障害
レム睡眠行動障害とは、眠っている間に大声で叫んだり、突然暴れたりするような異常行動が現れる疾患です。症状が強い場合には、自分自身を傷つけてしまったり、そばにいる家族に危害を加えてしまう恐れもあるため、注意が必要です。
このような行動は、認知症などの神経疾患が関係している場合や、一部のお薬の副作用として現れることもありますが、原因がはっきりしないケースもあります。
睡眠障害の検査・診断
まず問診を通じて現在の睡眠の状態や困っていることなどを丁寧にお伺いします。必要に応じて、血液検査などの身体的な検査を行うこともあります。
さらに詳しく睡眠中の状態を調べるために、「睡眠ポリグラフ検査」という検査が必要になることもあります。検査は、1泊入院で行うタイプのほか、ご自宅でできる簡易型の検査もあります。当院では簡易型ポリグラフ検査をスクリーニングとして行い、精査が必要な場合、対応可能な医療機関をご紹介いたします。
睡眠障害の治し方
 「心療内科や精神科に行くのはちょっと気が重い…」と感じている方でも、眠れないことに悩んでいるのであれば、一度ご相談ください。
「心療内科や精神科に行くのはちょっと気が重い…」と感じている方でも、眠れないことに悩んでいるのであれば、一度ご相談ください。
眠りに関する不安や悩みを話すだけでも、気持ちが少し軽くなり、睡眠の質が改善されるきっかけになることがあります。
何より大切なのは、「眠れないつらさ」を1人で抱え込まないことです。
不眠の悩みを放っておくと、症状が悪化するだけでなく、うつ病などの精神疾患を併発する恐れもあります。
睡眠障害は人それぞれ原因や背景が異なり、それに合わせた対応が必要です。
当院では、原因を丁寧に見極めたうえで、1人ひとりに合った対処法や治療法をご提案します。
ストレス
強い緊張やプレッシャーが続くと、心が休まらず、スムーズな入眠を妨げてしまいます。特に、几帳面な方や真面目な性格の方は、ストレスを抱え込みやすく、不眠の症状が現れやすい傾向があります。
精神的な不調
うつ病や不安障害などの心の病気が、不眠の原因になっていることもあります。その場合は、抗不安薬や抗うつ薬などを用いた治療が必要になることもあります。
お薬・飲食・嗜好品の影響
コーヒーに含まれるカフェインや、タバコのニコチンには覚醒作用があり、寝つきを妨げることがあります。また、降圧剤など一部のお薬が眠りに影響している場合もあるため、服薬状況の確認も行います。
生活リズムの乱れ
昼夜逆転のような不規則な生活が続くと、体内時計が乱れて不眠を引き起こすことがあります。特に日中の活動が減ってくると、夜の眠気がうまく訪れなくなります。
睡眠環境の問題
寝室の騒音や照明、温度・湿度などが快適でないと、ぐっすり眠れないことがあります。また、寝具の状態や衛生環境も、睡眠の質に影響を及ぼします。
薬物療法
睡眠障害のタイプに応じて、効果的なお薬を選んで治療を進めていきます。例えば、脳の興奮を抑える働きのあるGABA(ギャバ)に作用するお薬や、体内時計のリズムを整えるメラトニンに働きかけるお薬、覚醒ホルモンのオレキシンを抑えるお薬など、様々な選択肢があります。
お薬によっては副作用が出る場合もありますので、自己判断で服用を中断せず、医師の指示に従って正しく使用することが大切です。