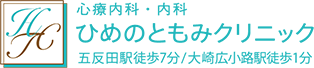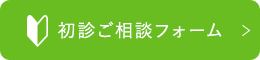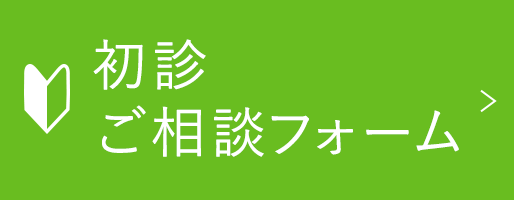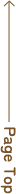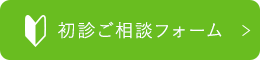機能性消化管障害とは
機能性消化管障害とは、英語で「functional gastrointestinal disorders(FGID)」と呼ばれるもので、口から肛門までの消化管の運動機能に関連した障害によって引き起こされるさまざまな病態を指します。具体的には、非びらん性胃食道逆流症(NERD:non-erosive reflux disease)、機能性ディスペプシア(FD:functional dyspepsia)、過敏性腸症候群(IBS:irritable bowel syndrome)などが含まれます。
機能性消化管障害の
種類と症状
機能性消化管障害にはさまざまな疾患が含まれますが、その中でも特に多く見られるものには「胃食道逆流症(GERD)」「機能性ディスペプシア(FD)」「過敏性腸症候群(IBS)」があります。また、これらの疾患は単独で発症することもありますが、複数の疾患が併発することもよくあります。
胃食道逆流症(GERD)・非びらん性胃食道逆流症・逆流性食道炎

胃酸や胃内容物が食道に逆流する状態を「胃食道逆流症(GERD)」といいます。逆流が発生していても、症状や炎症の程度は個人差があります。内視鏡で食道炎が見られない場合は「非びらん性胃食道逆流症(NERD)」、症状と炎症が両方確認できる場合は「逆流性食道炎」と診断されます。加齢や生活習慣が原因となり、胃と食道の接続部にある筋肉の機能低下が原因となることが多いです。
主な症状
- 胸やけ
- 胃もたれ
- みぞおちの痛み
- 胸のつかえ
- 呑酸(胃酸の逆流で酸味を感じる)
- 吐き気 など
機能性ディスペプシア(FD)

胃の痛みやもたれ、早期膨満感(すぐにお腹がいっぱいになる)などが慢性的に続くにも関わらず、内視鏡検査で異常が認められないものを「機能性ディスペプシア(FD)」と呼びます。胃は「貯留」「攪拌」「排出」という3つの機能を持っていますが、これらの機能に異常が生じることで機能性ディスペプシアが発症すると考えられています。
主な症状
- 慢性的な腹部の不快感(胃もたれ、早期満腹感、膨満感など)
- 胸やけ
- みぞおちの痛み
- 吐き気 など
過敏性腸症候群(IBS)
便通異常(便秘・下痢)や腹部の症状(腹痛・腹部膨満感)が慢性的に見られるにもかかわらず、検査で異常が認められない状態を「過敏性腸症候群(IBS)」と呼びます。特に通勤や通学時の電車内、職場や学校での不安やストレスが引き金となることが多く、ほとんどの場合、排便によって症状が軽快します。若い人に多く見られる疾患で、日本人の約1割がこの過敏性腸症候群を抱えているとされています。
主な症状
- 腹痛
- 便通異常(下痢と便秘を繰り返すこともある)
- 腹部膨満感 など
※排便によって症状が軽快するのが、過敏性腸症候群の特徴です
機能性胃腸障害の原因
機能性胃腸障害は、炎症や潰瘍などの明確な原因がないにも関わらず、不調が生じることがあります。この主な原因は「ストレス」です。脳の自律神経と腸管の神経は自律神経を通じてつながっており、胃や腸は他の内臓に比べて精神的・心理的な影響を受けやすい部位です。
機能性胃腸障害を「車の運転」に例えると、ストレスがアクセルを踏みすぎることにより下痢を引き起こしたり、逆にブレーキをかけすぎて便秘を引き起こしたりします。さらに、アクセルやブレーキのコントロールがうまくできないと、胃のもたれやすぐにお腹がいっぱいになる感覚が生じることがあります。
機能性胃腸障害の治し方
 当院は消化器内科ではないため胃カメラや大腸ファイバーのような設備はありません。胃や大腸に炎症や潰瘍などの病変がないこと、ピロリ菌感染がないことを消化器内科で確認するようお勧めしています。特にピロリ菌感染は胃潰瘍や十二指腸潰瘍だけでなく胃もたれや胃下垂などの大きな原因になります。
当院は消化器内科ではないため胃カメラや大腸ファイバーのような設備はありません。胃や大腸に炎症や潰瘍などの病変がないこと、ピロリ菌感染がないことを消化器内科で確認するようお勧めしています。特にピロリ菌感染は胃潰瘍や十二指腸潰瘍だけでなく胃もたれや胃下垂などの大きな原因になります。
異常がないと言われたにもかかわらず症状が長く続く方や、すでに長期に消化器内科の薬を服用しているのに改善しない方のご相談をお受けしています。
薬としては、一般的な胃粘膜保護薬や消化管運動機能改善薬の他、漢方、消化酵素などを使用します。原因や症状によって抗うつ薬などを選択することもあります。食事の内容を詳しく聴き取り、症状の原因になっている場合は修正していただきます。食べ方や食材を変えただけでかなり良くなる方もいます。ストレス対策も重要です。
なお、機能性ディスペプシアに使用されるアコファイドの処方は胃カメラを実施していることが条件となります。当院には胃カメラがありませんので、消化器内科と連携して治療いたします。
生活習慣の改善
胃腸への負担を減らすため、生活習慣や食生活の改善も治療の一環として重要です。
食事
- 規則正しい食生活を心がけ、三食しっかり摂る。食事はゆっくりと時間をかけて、よく噛んで食べる。
- 食べ過ぎは胃腸に負担をかけるので、腹八分目を目指す。
- 食事内容はバランスよく、脂肪や香辛料を控えめに。
- 消化の良い食品(卵、豆腐、鶏肉、うどん、白身魚など)を選ぶ。
- 食事の際にはリラックスした状態を心がける
その他
- 十分な睡眠を確保し、体をしっかりと休ませる。
- 運動や趣味の時間を持つことで、ストレスをためないようにし、解消する。